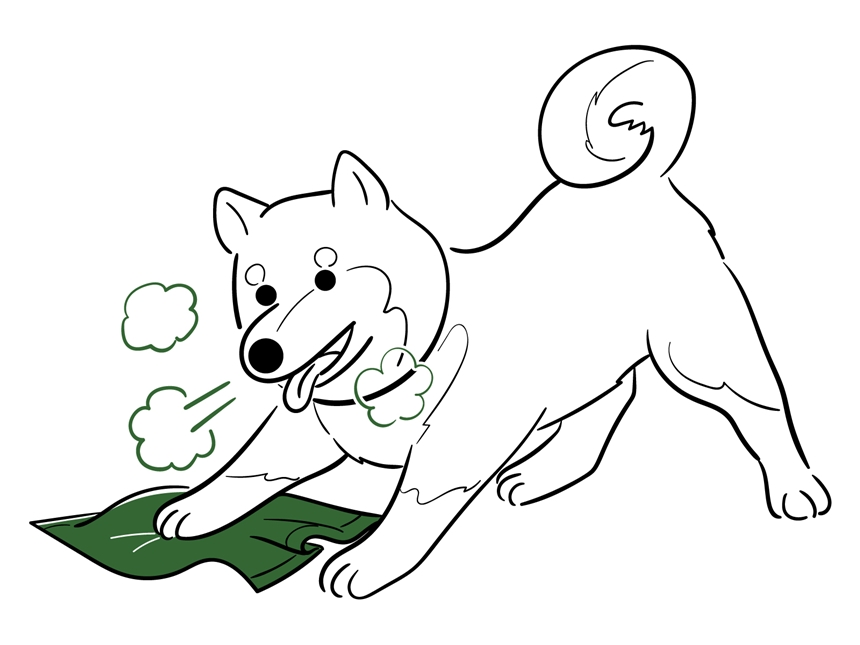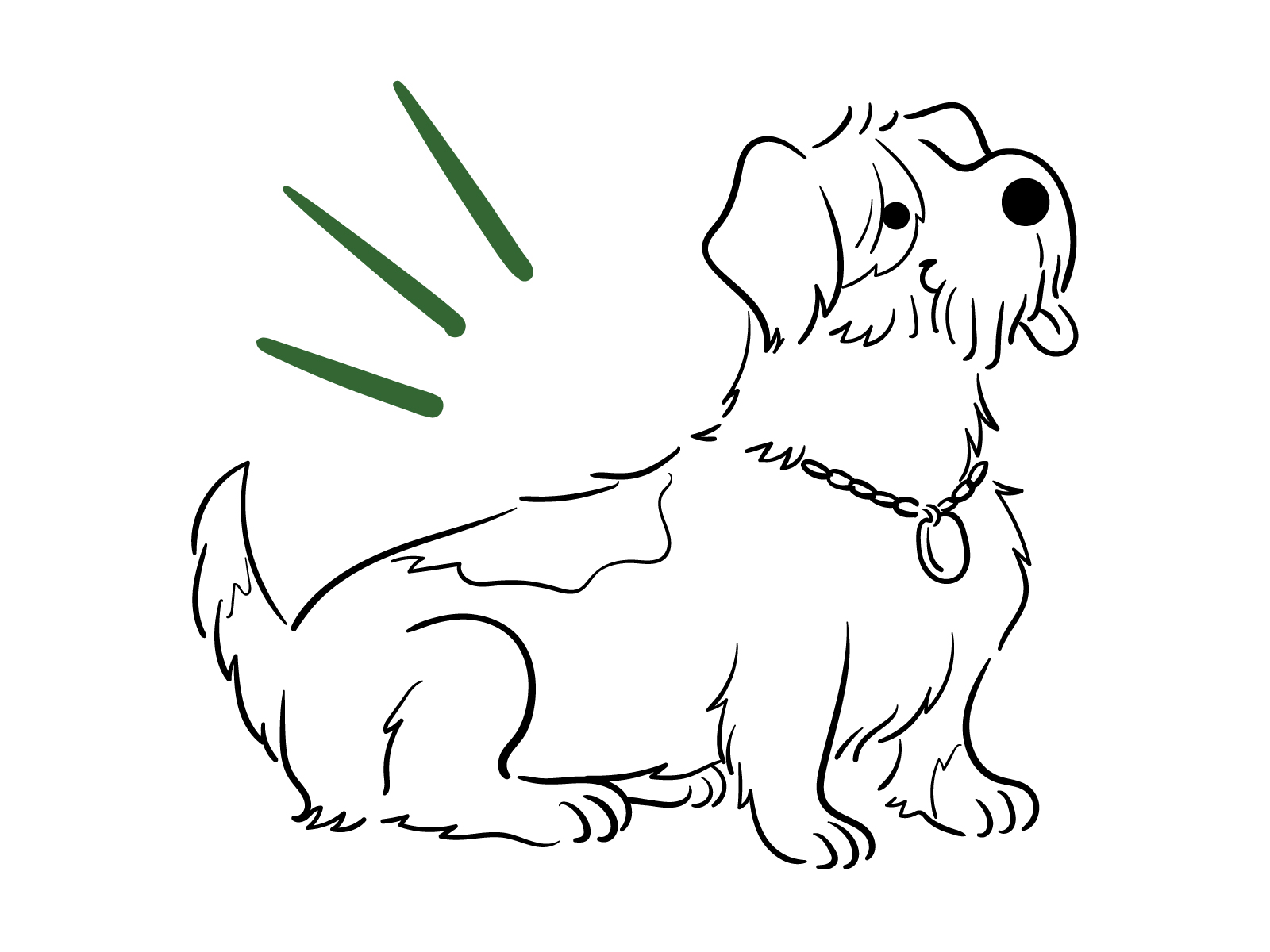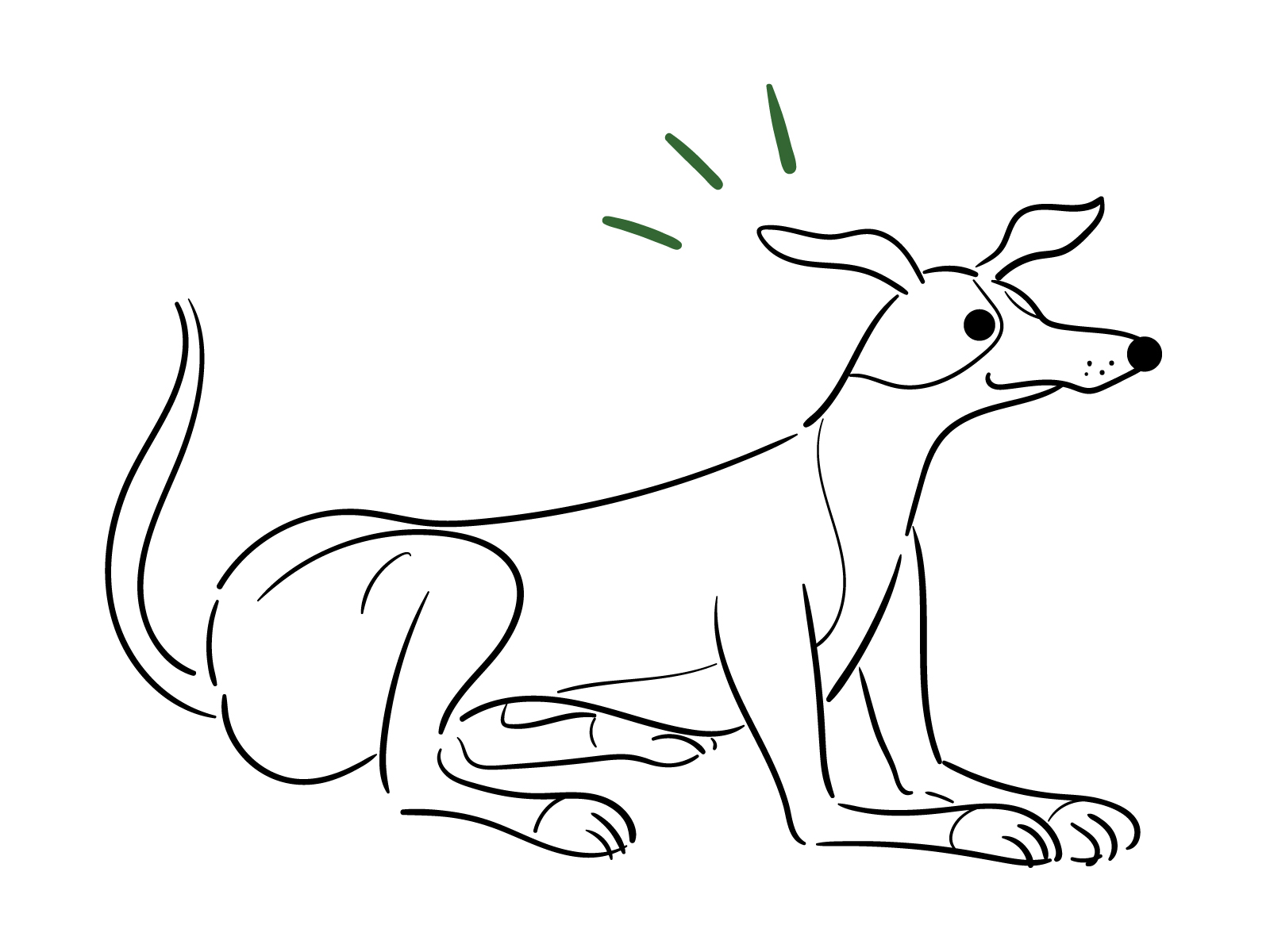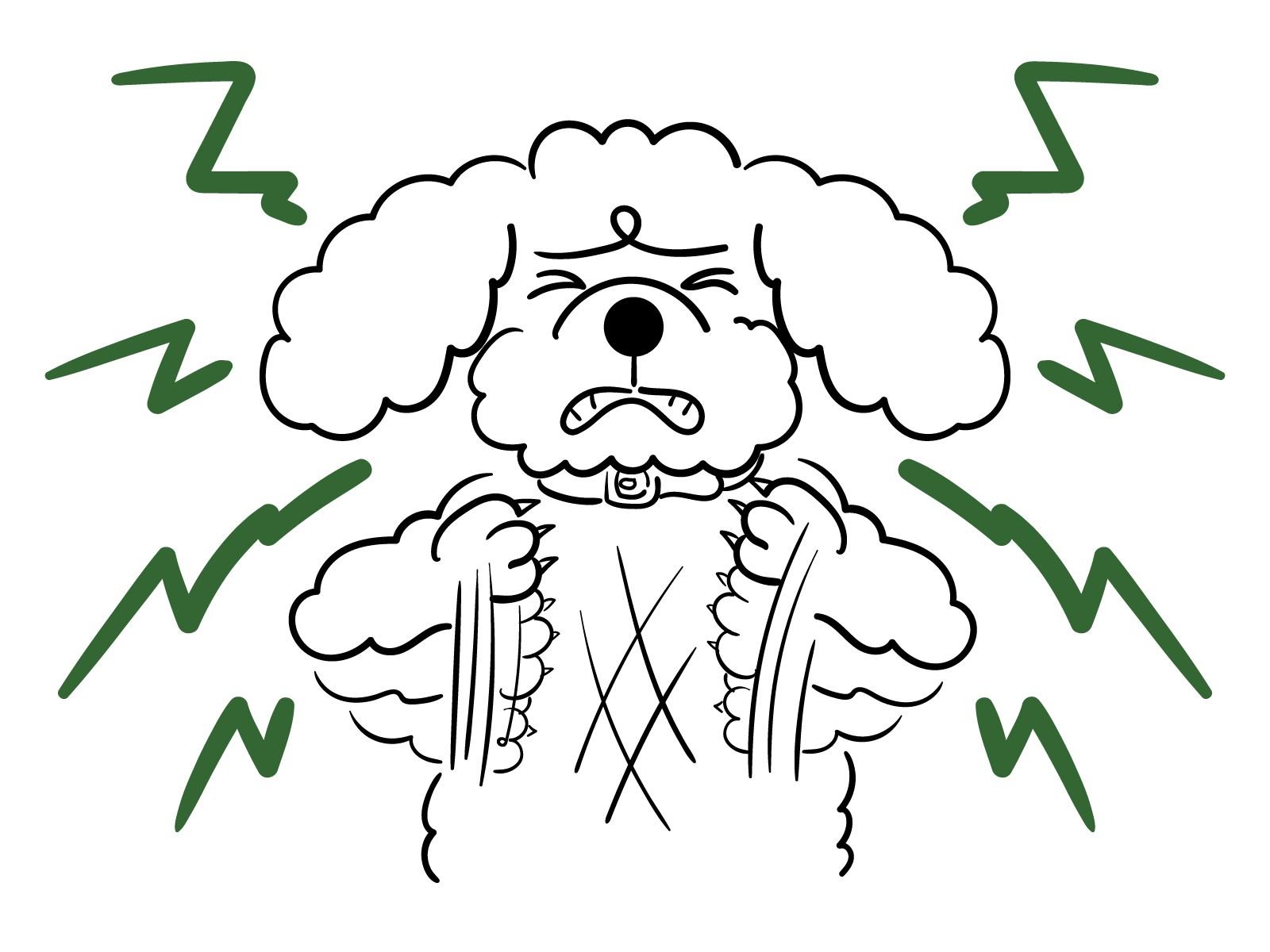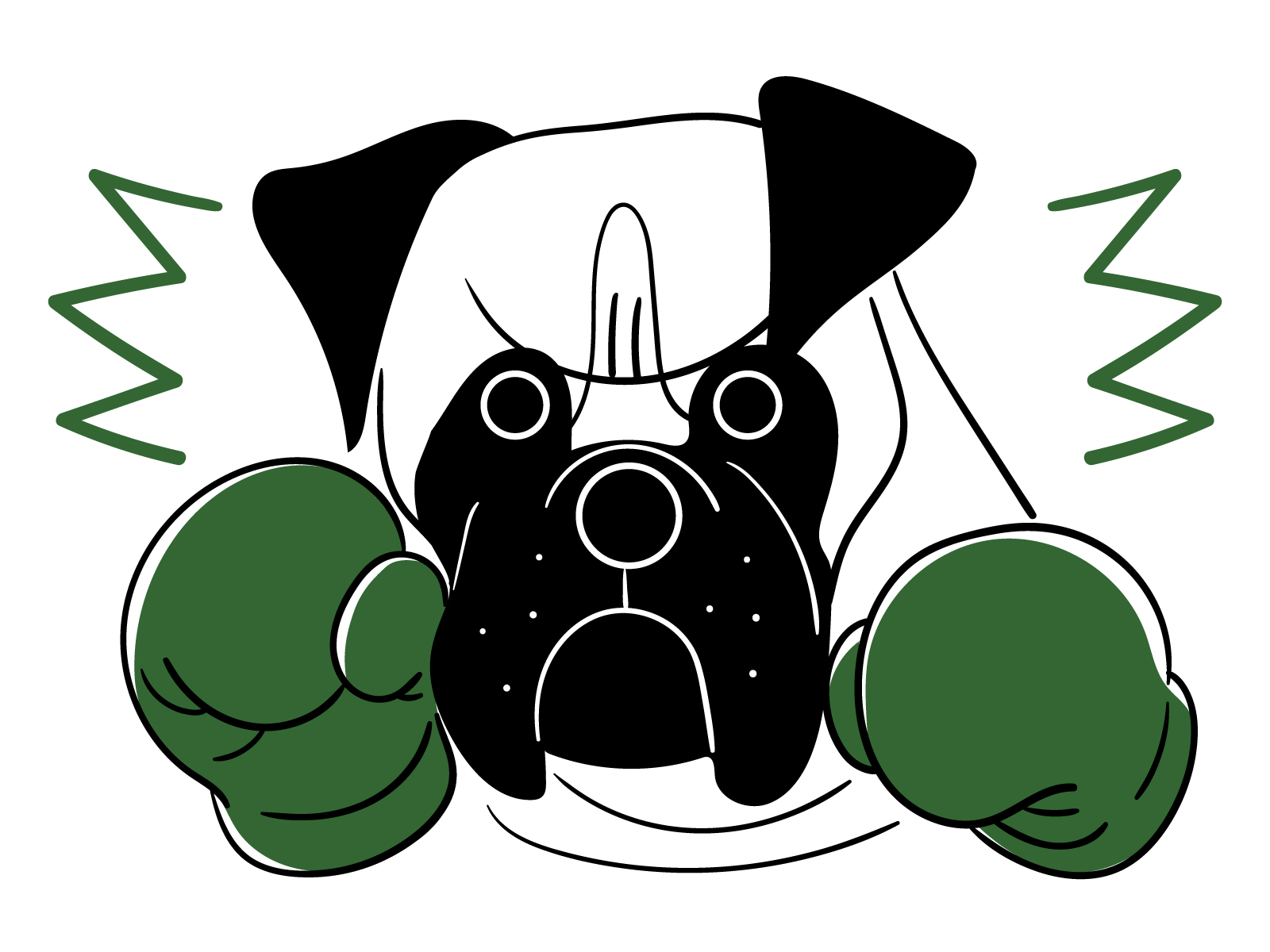愛犬が口呼吸をする姿を見て、次のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
「犬が口呼吸をする理由は?」
「犬の口呼吸は健康に問題ないの?」
「口呼吸ばかりしているときの対処法は?」
事前に口呼吸の理由を把握しておけば、病気の早期発見に繋がるかもしれません。
そこで今回は、犬が口呼吸をする理由や対処法について詳しくお伝えします。犬を飼っている方、これから飼う方もぜひご一読ください。
犬の正常な呼吸とは?
人間は鼻と口の両方で息をする生き物ですが、犬はどのような呼吸が多いのでしょうか。基本的に、犬は鼻呼吸を中心に行い、口呼吸はほとんどしません。ここでは、次の内容について紹介していきます。
- 犬の口呼吸はパンティングと呼ばれている
- 犬は口呼吸があまりできない
犬の口呼吸はパンティングと呼ばれている
犬も口呼吸ができないわけではありません。浅く早い呼吸をして、体温調節を行うことがあります。この体温調節のために行う口呼吸は「パンティング」と呼ばれる行動で、肺に空気が入ることはほとんどありません。
犬は汗をほとんどかかないので、パンティングによってうまく熱を逃がしているのです。ただし、短頭種と呼ばれるパグやフレンチブルドッグなどは、鼻呼吸がうまくできないケースがあります。そのため、苦しさから口呼吸が増えることがあるのです。
犬は口呼吸があまりできない
基本的に犬は食事を口で行い、呼吸は鼻で行うように機能を分けています。犬も口呼吸はできるのですが、機能を分けたほうが合理的であるため、口で息をすることが少ないのです。
ただし、何らかの疾患にかかっているときは、頻繁に口呼吸をするケースがあります。普段よりも口呼吸が多いときは、注意深く観察して疾患にかかっていないかチェックしておきましょう。
犬が口呼吸をする理由
普段は鼻呼吸が多い犬ですが、口呼吸をする機会もあります。犬が口呼吸する理由としては、次のとおりです。
- 体温調節するため
- リラックスするため
- 鼻づまりがおきている
それぞれの理由について、詳しく確認していきましょう。
体温調節するため
犬は人間と違い、発汗機能がほとんどありません。そのため、体温調節が苦手です。実際に、室内温度が上がり過ぎると熱中症になってしまう犬も多いので注意してください。
発汗機能の代わりに体温調節をする役割を持っているのが、「パンティング」と呼ばれる行動です。
前述した通り、パンティングは浅く早い口呼吸をする犬の行動で、体温上昇を防ぐ効果があります。室温が高いときはパンティングをする犬も多いので、異変に気付いたときは速やかにエアコンをかけてあげてください。
リラックスするため
人間と同じように、犬も感情の変化によって呼吸が乱れることがあります。例えば、怒りを覚えたときや体調不良のときは、自然と呼吸が早くなるケースが多いです。
そんなときに、犬は自分の気持ちを落ち着かせるためにパンティングを行います。頻繁にパンティングを行っているときは、「落ち着かない」「ストレスを感じている」などの可能性が高いです。
様子がおかしいときは、素早く環境を整えて、ストレスや体調不良の原因を取り除いてあげてください。
犬がストレスや体調不良を感じているときは、パンティング以外にも、吠えたり、あくびが増えたりします。愛犬の不調サインを見逃さないよう、普段からたくさんコミュニケーションを取ってあげてください。
鼻づまりがおきている
短頭種に多いのが、鼻づまりによる口呼吸です。鼻水や異物混入などで鼻づまりを引き起こすケースが多いので、様子がおかしいときは病院で診察を受けてください。
鼻がつまってしまうと、普段の鼻呼吸ができなくなるので、自然と口呼吸が増えます。寝ているときに、いびきや口が少し開いている状態が多い場合は鼻がつまっている可能性が高いです。
他にも、呼吸器や循環器系の疾患にかかっているときは、鼻呼吸で得られる酸素が少なくなるため口呼吸が増えます。犬は口呼吸で得られる酸素は少ないので、普段から口呼吸が多いときは注意してください。
犬が口呼吸しているときに考えられる病気
犬が体温調節以外の理由から口呼吸しているときは、病気にかかっている可能性があります。犬が口呼吸しているときに考えられる病気の種類は次のとおりです。
- 熱中症
- 心臓病
具体的に、どのような症状が出るのか詳しく解説していきます。
熱中症
体温調節が苦手な犬は、気温や室温が高いと熱中症に陥ってしまう恐れがあります。熱中症になれば、長時間もパンティングを続けることがあるので、おかしいと思ったときは病院で診察を受けてください。
熱中症になったときはパンティング以外にも、ぐったりしている、散歩に行きたがらないなどの症状が出ます。特に夏場は室温が高くなりがちです。常にエアコンを付けておき、犬が熱中症にならないよう対処してあげてください。
また、病気ではありませんが、ストレスを溜め込んでいるときにも口呼吸は増える傾向があります。初めて行く場所や大きな音がする環境では、犬がストレスを感じやすいです。
あくびが多かったり、尻尾をお腹のほうに丸めたりする行動が増えたときは、ストレスのサインなので注意してください。
心臓病
日常的に犬が口呼吸をしている場合、心臓疾患にかかっている恐れがあります。口呼吸をしていることで疑わしい心臓病は、以下の通りです。
- 僧帽弁閉鎖不全症
- 心室中隔欠損症
僧帽弁閉鎖不全症は、弁がうまく機能しないことから血流が乱れてしまう病気です。主に小型犬がかかりやすい病気と言われています。
心室中隔欠損症は心臓に穴が空く病気で、先天性のものが多いです。治す手段としては、手術や投薬を行う必要があるので、動物病院で適切な対応を受けましょう。
どちらも口呼吸を誘発させるほど、苦しそうに息をする傾向が強いので、様子がおかしいときは動物病院で診察を受けてください。
犬が口呼吸しているときの対処法や治療法

犬の口呼吸が続くときには、次のような対処が必要です。
- 動物病院で診察してもらう
- 口呼吸の原因を取り除く
具体的な対応について、詳しく解説していきます。
動物病院で診察してもらう
犬の口呼吸を行う頻度が多いときは、動物病院で診察してもらうのがよいでしょう。特に次のような症状が出ているときは、注意が必要です。
- いつもより呼吸が早い
- 散歩の時間でも動こうとしない
- よだれが多い
病気や体調不良が原因で口呼吸をしている場合、他にもいつもと違う行動を取るケースがあります。少しでもおかしいと感じたときは、動物病院へ足を運び、診察を受けてください。
口呼吸の原因を取り除く
犬の口呼吸を治療するためには、以下の方法で原因を取り除く必要があります。
- 酸素療法
- 薬物療法
それぞれの治療法について、詳しく紹介していきます。
酸素療法
濃度の高い酸素を犬に吸引してもらい、息苦しさを緩和させる治療法です。人間の場合は、酸素マスクを着用しますが、犬の場合はマスクの着用は困難になります。
そのため、犬の酸素療法では、濃度の高い酸素室に入り治療するのが一般的です。酸素室をリースし、自宅で治療を行うケースも多い治療法となっています。
薬物療法
息苦しさを薬剤で緩和させる治療法です。主に気管支拡張剤やステロイドが含まれている抗炎症剤を活用するケースが多いでしょう。
ただし、口呼吸の原因である病気の種類によっては、適している薬剤は異なります。動物病院で診察を受けて、正しい薬剤を処方してもらってください。
口呼吸をしやすい犬の特徴
基本的に犬は口呼吸をほとんどしません。しかし、以下に該当する犬は口呼吸が多い傾向があります。
- 短頭種
- 老犬
なぜ口呼吸をしやすいのか、理由について解説していきます。
短頭種
鼻が短い短頭種は気道が他の犬よりも狭いため、呼吸がしづらい傾向にあります。より多くの酸素を取り入れるため鼻呼吸と同時に、口呼吸をするケースが多いです。
特に短頭種は、次のような呼吸器系の疾患にかかりやすいので注意してください。
- 狭窄性外鼻孔
- 気管虚脱
- 軟口蓋過長症
呼吸器系の疾患にかかったときは、口呼吸が多くなるので普段から愛犬の様子をチェックしておきましょう。
老犬
加齢が原因で呼吸器系の働きが悪くなり、口呼吸が増えるケースがあります。また、呼吸器系や循環器系の病気にかかりやすいので、日頃から愛犬の様子は確認しておきましょう。
犬が口呼吸しているときは病院で診察を受けよう
基本的に犬は鼻呼吸を行い、口は食事をするためだけに使用することが多いです。しかし、体温調節を行うために、口呼吸をする機会も多く見受けられます。
他にも、鼻づまりや呼吸器系の疾患が原因で口呼吸をする犬もいるので、いつもと愛犬の様子が違うときは速やかに病院へ足を運び、適切な治療を受けさせてあげてください。
執筆:いぬのあのね編集部
イラスト:ヴァイクセルブラウン花咲季
<スポンサーリンク>
新着記事




<スポンサーリンク>